| 宇治紀行 ― その7 ― The City of Power Station ≈≈≈ UJI ≈≈≈ パワースティション(発電所)の町 〜 宇治市 柳橋水車図 と 筒車(つつぐるま) |
|
宇治橋を背景に川風に揺れる柳、水車を描いた「柳橋水車図」は宇治川周辺の風景として知られていました。古来より、川風(川霧)・水車(筒車)・網代木などは、宇治の風物詩でした。 |
|
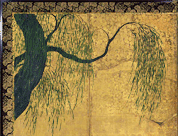 |
 |
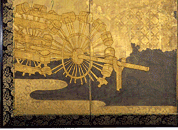 |
|
| ↑早瀬を利用して川水を汲上げている水車 |
|

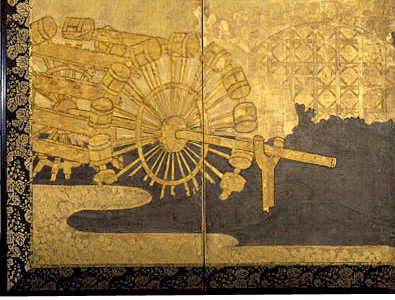 |
|
| 安土桃山時代に描かれた長谷川等伯の「宇治川柳橋水車屏風」を ヒントを得て動画にしました。 |
|
─その1─ ─その2─ ─その3─ ─その4─ ─その5─ ─その6─ ─その7─ ─その8─ 番外編 |
|
| ↑ バックナンバーもあります。 ↑ ご覧下さい。 |
| ★ The City of Power Station ≈≈≈ UJI |
|||||||
| 古くは『万葉集』『古事記』『日本書紀』に始まり、『源氏物語』や『平家物語』の素材になった宇治は、いにしえより都の人々の心をとらえ、和歌に絵画にさまざまな作品が伝わります。柳、橋、水車、この三つが描かれていれば、それは宇治だといわれたほどで、特に有名なのが、安土桃山時代に長谷川等伯が描いた『柳橋水車図(りゅうきょうすいしゃず)』で、その典型的な作品です。 宇治の先人の里人の匠の技
宇治と水車にまつわるお話が吉田兼好の『徒然草』の五十一段に登場します。嵐山の大堰川の里人に水車を作らせたところ、うまくいかず、宇治の里人を召集して作らせると、容易く水車を作り、しかも見事に水を汲み入れたというものです。何事につけてもその道を究めた者はすばらしく、その専門家に任すべきだと、宇治の里人の水車作りの技術を称えています。 当時、宇治では宇治川の急流を利用して、筒車(つつぐるま)と呼ばれる水車が造られ、それによって平等院の阿字池や近隣の田畑に豊富な水を供給していました。柳に水車の風情こそ在りし日の面影を偲ぶばかりですが、豊かな宇治川の流れは今も健在で、宇治市には、宇治発電所、天ヶ瀬発電所、喜撰山揚水式発電所の三つ水力発電所があり、電力を供給しています。 |
|||||||
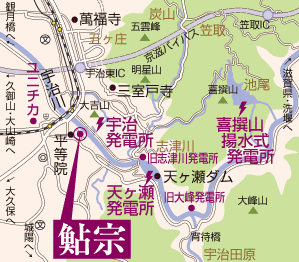 |
|||||||
|
|||||||
 宇治発電所 (2006宇治灯り絵巻の時の様子) |
そもそも宇治発電所は琵琶湖との落差75mを利用したもので、瀬田川洗堰から支水した水でタービンは水車と同じようにタテに回転しています。宇治川の上流にあたる琵琶湖の瀬田は大阪城天守閣の高さがちょうど同じくらいで、瀬田川を渡る東海道新幹線はその天守閣の上程の高さを走っていることになります。 また、宇治市内にはユニチカ宇治事業所内にも天然ガスの自家発電設備が導入され、天ヶ瀬ダムと同量の電力を発電しているとともに、それは奈良県全域のガスの消費量とほぼ同じ量にあたります。 今もなお、そしてこれからも、宇治は“パワースティションの町”なのです。 |
||||||
宇治紀行 1 宇治紀行 2 宇治紀行 3
宇治紀行 4 宇治紀行 5 宇治紀行 6
宇治紀行 7 宇治紀行 8
  |
あいそ(あゆそう)
〒611-0021
宇治市宇治塔の川3-4
不定休
TEL:0774-22-3001
FAX:0774-22-3003
E−メール
宇治紀行
その1
平家物語
「宇治川先陣争い」
その2
浮島十三重の石塔
その3
宇治の網代木
その4
宇治拾遺物語
「鼻」
その5
種田山頭火
“宇治平等院 三句”
その6
≈ 宇治 ≈ 秋の行事 ≈
その7
パワースティション
の町〜宇治
その8
冬の宇治
番外編
当店の桂垣
〜(^_^)〜
みてください
Copyright© 2005
料理旅館 鮎宗 ®.
All rights reserved.

