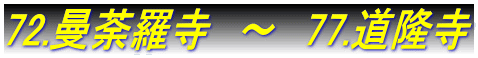
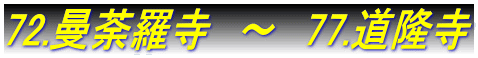
 <写真1 門先屋旅館朝食> |
・・・七十二番曼荼羅寺へ 0.1km・・・ 2月13日(日)朝6:30起床。布団をたたみ身支度をして一階の広間へ向かった。朝食<写真1>は7時からで声をかけるとみそ汁を持って来られた。シーフードカレーは今朝も用意されていたが朝は軽くで済ませた。 部屋を出て宿代を支払ったあと、おかみさんに捨身ヶ嶽に行くことを言うとザックは置いていくようにと言って頂いた。ザックを玄関に置かせて頂き、7:37門先屋を出発した。 曼荼羅寺山門<写真2>は、門先屋のすぐ隣りにあった。両脇の仁王様は朝日を浴びて輝いておられた。境内<写真3>は誰もおられず静かだった。境内の隅で青島みかんが無人販売されていた。昨日お接待で頂いたものと同じもののようだった。伊予柑ではないとおっしゃっておられたので多分これだろう。 本堂と大師堂でお参りをしているとお参りの方がやって来られた。駐車場からの近道を通って来られたようであった。お参りのあと納経して頂いた。 72曼荼羅寺  |
|||
 <写真2 曼荼羅寺山門> |
||||
 <写真3 曼荼羅寺境内> |
 <写真4 出釈迦寺へ> |
|||
| ・・・七十三番出釈迦寺へ 0.6km 合計0.7km・・・ 7:55曼荼羅寺を出発し出釈迦寺に向かった。門先屋玄関前まで戻りそのまま四差路を真っ直ぐ上がった。<写真4>しかし上っていく道が途中でなくなってしまったので民家の畑の中を通らせて頂き遍路道と合流した。緩やかな坂を上り8:05出釈迦寺山門<写真5>に到着した。 本堂でお参りをしたあと、大師堂<写真6>に行くとお堂の中から般若心経が聞こえた。お寺の方の朝のお勤めのようだった。納経所ではお寺の方から「歩かれているのですか?」と訊かれた。「はい」と答えると、「歩きと自転車の方にはジュースをお接待してるの」とおっしゃられ、150円を下さった。 有り難く頂戴し、「これから奥の院に行って来ます」と言うと「電線に沿って、お気を付けて」とアドバイスをして頂いた。そして境内の自販機で缶コーヒーを購入しベンチで飲んだ。境内を奥に向かい捨身ヶ嶽遥拝所<写真7>を経て8:23出発した。 73出釈迦寺  |
 <写真5 出釈迦寺山門> |
|||
 <写真6 出釈迦寺大師堂> |
||||
 <写真8 木製ベンチにて> |
 <写真7 捨身ヶ獄遙拝所> |
|||
 <写真9 奥の院山門> |
・・・我拝師山往復 2.8km 合計3.5km・・・ 燈籠がいくつも並ぶアスファルトの道を上った。燈籠が途切れると、弘法大師御加持水「柳の水」がありベンチも置かれていた。さらに上ると車は通行止で無断通行車輌は罰金10万円との大きな看板があった。上から山登りの恰好をされた方が2名下りて来られ挨拶をした。 電線に沿ってどんどん上り、歩きの地道が車道と合流すると木製ベンチ<写真8>があった。そこは草木が途切れ見晴らしのいい場所だった。弥谷寺から続く山々や多度津の町、さらにその向こうには瀬戸内海が見えた。 車道をさらに上り、我拝師山と中山の鞍部にある奥の院山門<写真9>に8:51到着した。奥の院本堂で手を合わせてから、本堂横のトンネル状の通路<写真10>をくぐった。ここには「岩倉大師・御行場入口」との木札があった。トンネル状通路を抜けるとその先は、”登嶺者の方へ これより行場は当山の大霊域により飲食・危険行為は禁止です。 注意して登嶺して下さい。”と白い看板が立てられ、白いロープも張られていた。<写真11> この先、岩場となっているようなので、納経帳やその他のものをスタッフバッグに入れ、金剛杖とともに、その場に置いて白いロープをくぐった。 岩場には適当な足場や手懸りがあった。さらに登ると鎖が架けられていた。<写真12>岩場や鎖場を登り、9:01捨身ヶ嶽禅定<写真13>に到着した。小さな幼いお顔の坐像があった。 捨身ヶ嶽については、「へんろみち保存協力会編 四国遍路ひとり歩き同行二人」より引用させて頂く。”弘法大師七歳の御時、「我もし佛の道を得て衆生済度の願満たば救い給へ、意願契はぬなれば命失うとも悔ず」と、この地で捨身の修行をされ、釈迦如来の御加護を賜ったという。出釈迦寺の寺号が生じた由緒ある霊場である。” 登嶺道はそのさらにその奥に続いていたのでさらに登った。岩場を過ぎるとなだらかな林の中の道となり、我拝師山山頂(標高481m)<写真14>に9:10到着した。山頂には三角点や立て札が立てられていたが、樹林に覆われていたので展望はなかった。 雪が降ってきた。それも粉雪だった。止まっていると寒いので、早々に引き上げることにして9:13下山を開始した。 鎖場や岩場を下り奥の院本堂まで戻り、トイレを借りた。トイレの個室には、”急ぐとも心落ち着けちらすなよ吉野の桜(はな)も散れば東西南(きたなし)”と川柳があった。 出釈迦寺から奥の院往復の間、登山の方2名と出会っただけで一台の車とも出会わなかった。10:03出釈迦寺の捨身ヶ嶽遥拝所まで戻ると大勢の団体のお遍路さんがおられた。先達らしき方が捨身ヶ嶽や奥の院の由来などを話されたいたようでちょうどそこへ僕が戻って来たようだった。先達の方が「奥の院をお参りされてきたのですか?」と訊かれたので「はい、捨身ヶ嶽と我拝師山の山頂にも行ってきました。」と答えると大勢の方々から拍手や歓声を頂いた。納経所の方にも参拝と登下山の無事を報告に行くと、記念にと手拭いを下さった。 |
|||
 <写真10 本堂横の通路> |
||||
 <写真11 行場入口> |
||||
 <写真12 鎖場> |
||||
 <写真13 捨身ヶ嶽禅定> |
 <写真14 我拝師山山頂> |
|||
| ・・・七十四番甲山寺へ 2.8km 合計6.3km・・・ 出釈迦寺から団体の方々と一緒に下り、10:14門先屋旅館<写真15>に帰館した。預かってもらっていたザックを取りに中に入ると、おかみさんが出てこられ、ホットコーヒーとお菓子をお接待して頂いた。おかみさんと奥の院のことなど話しをした。大きなザックを背負われた方が前の道を通られた。野宿で通しの方のようだ。 ゆっくり休憩させて頂き、10:44門先屋旅館を出発。小さいながらも形よく盛り上がっている甲山目指して歩き出した。住宅地を抜け田んぼの中に入ると、道はくねくねと曲がっていた。<写真16> 車道を渡ると道は真っ直ぐ甲山寺へ向かっていて甲山の背後には、同じ円錐形でもより盛り上がり方が大きな讃岐富士が見えた。 11:12甲山寺山門<写真17>到着。山門をくぐると山が迫っていた。辺り一帯は平地であるが境内は山寺の雰囲気があった。本堂<写真18>と大師堂でお参りをしていると、何人かの方々が来られた。見るとお参りに来られたご高齢の方や車椅子の方をボランティアの方が介助されておられた。 74甲山寺  |
 <写真15 門先屋旅館の角> |
|||
 <写真16 くねくね道> |
||||
 <写真18 甲山寺本堂> |
 <写真17 甲山寺山門> |
|||
 <写真19 吠える犬> |
・・・七十五番善通寺へ 1.6km 合計7.9km・・・ 11:28甲山寺を出発。川に沿って歩いたり川を渡ったりして住宅の中を歩いた。民家の犬は姿勢を屈め僕に向かって吠え立てた。<写真19>看護学校の前を通過し交差点に出た。真っ直ぐ行くと仙遊寺で善通寺へはこの交差点で右に折れる。交差点の左手には宮川製麺所があった。弊掲示板に「お勧め」を投稿して頂いていたので立ち寄ろうとしたが、「本日は終了しました」との看板があった。 善通寺へ遍路道を真っ直ぐ向かった。県道48号線を横断し、たこ焼き屋や仏具店、牛乳販売店など民家に中に混在する様々な店<写真20>を見ながら、11:51善通寺二十日橋<写真21>に到着した。 御影堂へ向かう二十日橋の両脇には托鉢のお遍路さんがおられ般若心経を唱えておられた。僕は順序通りまず本堂に向かった。本堂への参道では、たいやきやその他おみやげものの露店が出ていた。門を入ると広い敷地の右手には巨木があった。正面には鳩の群れと五重塔。本堂<写真22>は二重の屋根でお参りの方が途切れることがなかった。 本堂でお参りをしたあと二十日橋を渡り御影堂(大師堂)へ向かった。御影堂は本堂以上に大きなお堂であった。拝観料として500円必要だったが戒壇めぐり<写真23>もした。戒壇めぐりは、階段を下りて真っ暗な中を左手を伸ばして壁をつたい歩いていく。100mほどの距離であるが、途中明るい中央広間があり、そこではお大師様から「私の願い」を話して頂いた。 戒壇めぐりのあと宝物館も見学し、二十日橋から本堂前を経て12:48善通寺赤門を出発した。 75善通寺  |
|||
 <写真20 たこ焼き屋> |
||||
 <写真21 善通寺二十日橋前> |
||||
 <写真22 善通寺本堂> |
 <写真23 御影堂、戒壇めぐり入口> |
|||
| ・・・七十六番金倉寺へ 3.8km 合計11.7km・・・ 赤門からきれいな街路を真っ直ぐ歩き、途中から狭い遍路道に入り、13:08JR予讃線の線路下<写真24>を頭上注意して通過。畑の中を歩き、交通量の多い車道を車に気を付けて横断した。讃岐富士の横に赤と青のチューブが見えた。ウォータースライダーのようだ。<写真25>13:27高松自動車道をくぐった。腹が減って来たのでどこかで昼食にしたかったが、遍路道沿いには店はなかった。車道を歩けばいろいろありそうだったがそのまま歩き13:39金倉寺山門<写真26>に到着した。 仁王像に睨まれながら山門をくぐり境内<写真27>に入った。鐘がとても高いところにあり、その建物の柱も高かった。本堂には団体のお遍路さんがおられお参りされていた。本堂前には、木の玉が数珠繋がりになっていてそれをまわすものがあり、まわすと木の玉が落ちてきて「カチッ」といい音がした。 本堂と大師堂でお参りし納経所へ向かった。歩きらしい方々が2名、納経所前のベンチで休まれていた。お二人連れだったのでお声を掛けなかったが納経所から出るとすでにおられなくなっていた。 腹が空いていたので納経所前の自販機で缶コーヒーを購入し、透明なビニールシートで風を避けたベンチで手持ちのパンを食べ昼食とした。 76金倉寺  |
 <写真24 頭上注意> |
|||
 <写真25 讃岐富士とウォータースライダー> |
||||
 <写真27 金倉寺境内> |
 <写真26 金倉寺山門> |
|||
 <写真28 道しるべ> |
・・・七十七番道隆寺へ 3.9km 合計15.6km・・・ 金倉寺を14:16に出発。パチンコ店駐車場のゲートをくぐり遍路道は続いていた。14:26高架となっている国道11号線をくぐった。遍路札や遍路シールだけでなく、様々な道しるべ<写真28>がありそれらを頼りに歩いた。豊原郵便局前、豊原小学校、多度津自動車学校と順に通過して15:10道隆寺山門に到着した。 山門をくぐった正面が本堂だった。誰もおられない境内の杖立てに二本金剛杖が立てられていた。誰かの忘れ物だろうか?僕は以前、徳島県の15番国分寺で金剛杖を置き忘れてしまい、引き返したことがある。歩きの場合、忘れ物を取りに引き返すのはとても辛いことだ。 本堂<写真29>と大師堂<写真30>でお参りをした。時間を勘案すると今回のお四国歩きは、ここ道隆寺が最後の札所となるので、今回の道中も無事だったことを報告しお礼のお参りもした。 77道隆寺  |
|||
 <写真29 道隆寺本堂> |
||||
 <写真30 道隆寺大師堂> |
 <写真31 丸亀市へ> |
|||
| ・・・JR宇多津駅へ 6.2km 合計21.8km 累計1058.1km・・・ 道隆寺を15:33に出発。交通量の多い県道21号線を西に向かい、15:42丸亀市に入った。歩道はところどころ狭く<写真31>車が来るたびに身構えることもあったが、ほとんどの車は歩きの僕を配慮して運転された。 西汐入川の塩屋橋を渡るとビルなど高層建築物が増えた。今回はJR丸亀駅を目標として来たが、もう一駅先のJR宇多津駅まで歩くことにした。 遍路道は別冊地図の通り、突き当たり、右へ曲がり、すぐ先の南条町の交差点を左折してさらに市街地を歩いた。16:26丸亀市役所の横から丸亀城<写真32>が見えた。さらにその先、土器川の蓬莱橋からは讃岐富士<写真33>が見えた。JR丸亀駅で打ち終えとしなかったのは、この丸亀城と讃岐富士を見たかったからなのだ。そして宇多津町に入り左折して17:05JR宇多津駅<写真34>に到着した。 白地に青のJR四国をイメージした駅舎は真新しかった。この駅で松山方面からやって来た特急列車は高松行きと岡山行きに切り離される重要な駅である。 僕は大阪市内までの乗車券と新幹線&特急券を購入するため、みどりの窓口に並び切符を購入して改札を通った。そして17:23発の特急しおかぜ24号に乗車し、往路と同じルートでJR新大阪駅<写真35>を経由して京阪宇治駅から帰宅した。 JR宇多津駅  |
 <写真32 丸亀城> |
|||
 <写真33 讃岐富士> |
||||
 <写真35 JR新大阪駅> |
 <写真34 JR宇多津駅> |
|||
| 2005.2.13(日)の会計 | 金額 | |||
| 門先屋旅館 一泊二食 |
7350円 | |||
| 納経料6寺 | 1800円 | |||
| 戒壇めぐり | 500円 | |||
| 缶コーヒー | 120円 | |||
| JR乗車券 宇多津→大阪市内 |
4020円 | |||
| JR乗継自由席特急券 宇多津→岡山 |
260円 | |||
| JR新幹線自由席券 岡山→新大阪 |
2410円 | |||
| 京阪電車 京橋→宇治 |
390円 | |||
| 計 | 16850円 | |||
| 合計 | 42092円 | |||
| 累計 | 554676円 | |||
| ☆ 38日目のページに戻る ☆ | ★ 40日目(次回)のページに進む click ! ★ | |||
2005年3月2日 記
 |
 |
|
| お遍路記録へ戻る | TOPへ戻る |