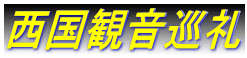
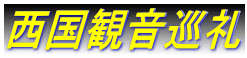
 <写真1 醍醐寺総門> |
・・・ 西国十一番上醍醐寺へ ・・・ 2003年11月3日(月)文化の日。京阪バス「醍醐三宝院前」で7:40下車。 過去の経験によると、この日は、晴れやすい”特異日”であるが、今年に限っては、朝から雨である。 バス車内で、いつものようにレインウェアを着用した。 今回は、職場同僚の伊三郎氏と二人連れである。彼は三年半をかけてこの夏、四国八十八ケ所を結願された。歩きのことも巡礼のこともよく知っておられる。 このバス停で降りたのは、僕たち二人だけだった。秋の観光シーズン真っ盛りであるが、雨の早朝、人はほとんどおられない。 醍醐寺総門<写真1>をくぐり、色づきはじめた木々の間の参道を歩いた。 参道の脇には屋台の骨柱が組まれていた。この連休中、賑わったはずだが、ゴミひとつ落ちていない。手入れがゆきとどいている。 仁王門前到着。両脇をかためられた仁王様<写真2>に圧倒される。三宝院境内へは、仁王門をくぐり真っ直ぐだが、今日はここを右に折れた。 三宝院境内を左手に見ながら歩き、7:55上醍醐寺への参道に入った。金剛杖が用意されていて、伊三郎氏はここで金剛杖を借用された。五体の不動像に水をかけ、清められている地元の方がおられた。早朝、雨の中、ここまで来られたようだ。 鬱蒼とした森の中、上醍醐寺への参道<写真3>は続いた。 しばらくは歩きやすい落ち葉の参道が続いた。丁石もあった。一丁から始まり、途中十五丁まで確認したが、多分、二十丁までなのだろうか? 参道は途中から石段となり、しばらく上って8:20不動の滝到着。ここには、標識がおかれていた。標識には、ここから札所の准胝堂(じゅんていどう)まで1.1km、30分。三宝院駐車場まで1.7km、33分とあった。三宝院から上醍醐まで約60分なので、所要時間でおよそ半分のところなのだろう。 ここからさらに石段の参道を登り、8:27霊樹”相生の杉”<写真4>通過。平坦路となって、上醍醐寺務所前を過ぎ、三室戸寺(炭山集落)からの参道と合流した。そこから石段を上がり、醍醐水のお堂<写真5>に8:50到着した。 |
|||
 <写真2 仁王門の仁王像> |
||||
 <写真3 上醍醐寺への参道> |
||||
 <写真4 霊樹”相生の杉”> |
 <写真5 醍醐水のお堂> |
|||
| ・・・ 西国十一番上醍醐寺にて ・・・ 醍醐水のお堂から札所への案内に沿って石段を上ると札所のある准胝堂<写真6>に8:55到着した。お参りをしたあと、納経所の方を見た。ここには、ネットを通して知り合いになることができたお坊さんがおられるかも知れない。 その方は、僧侶としてのご自身の役割を強く感じられ、実践されておられる尊敬すべき方である。お声掛けさせて頂こうと思ったが、どの方もお忙しそうにしておられたので、気後れしてしまい、失礼してしまった。 さらに境内の奥へと進み、9:05五大力尊<写真7>のある五大堂<写真8>に到着した。 始まったばかりの紅葉とあたり一面の霧。なんとも幻想的であった。 上醍醐寺へは、これまでも何度となくハイキングで訪れたことがある。ここから北へ向かい、横嶺峠を経て高塚山や、さらにその先の牛尾観音や音羽山、千頭岳にも登った。またその逆コースも。 しかし、今回は巡礼としてここまでやって来た。 このお山はとてもいい。ハイキングとしても巡礼としても。気が付けば、僕とこの山とは、十年来の付き合いとなってしまった。 想いにふけっているうちに雨もあがったようなので、レインウェアを脱いだ。そしてトイレも借り、さらに奥へと進んだ。 如意輪堂前を通り、9:20開山堂のある醍醐山頂(標高450m)<写真9>に到着。晴れていれば、山科盆地や宇治市内、さらにその向こうには京都盆地も望めるはずだが、今回眺望はない。山頂部は全くの雲の中だった。 9:25西国十二番岩間寺への標識に従って東へ下山した。登りの大半は、石段であったが、ここからは岩と土の山道<写真10>だ。濡れた岩に足を取られないよう気を付けながら下山した。 木組みの橋があった。少し傾いていて滑りやすそうなので順番に渡った。橋を渡ってからは、谷を左手に、谷川の音を聞きながら下った。下りは早い。だんだんと谷が広がってきたなと思っていると、突然、民家が現われた。 道路に停めてある車にストックや金剛杖をぶつけないよう民家の敷地を通り、笠取八景のひとつである「宝篋塔(ほうけんとう)の時雨」という石碑のある西笠取登山口<写真11>に9:45出た。 |
 <写真6 上醍醐寺准胝堂> |
|||
 <写真7 五大力尊> |
||||
 <写真8 紅葉と五大堂> |
||||
 <写真10 笠取への下山道> |
 <写真9 醍醐山山頂> |
|||
 <写真11 西笠取登山口> |
・・・ 西国十二番岩間寺へ ・・・ ここからはアスファルトの車道を西笠取川沿いに下った。田んぼが広がる。しばらく歩くと右手に10:00アクトパル宇治<写真12>が見えてきた。数年前、子供が保育園からのお泊まり保育でお世話になった。 その時は、子供にとってはじめて外泊だったので、夕方、そっと見に来たのを思い出す。ここは星空も綺麗に見えるので天体観測設備も充実しているらしい。 ここから東笠取へは、谷筋から外れ、左へ小さな峠の方へ向かう。車道が続くが、地形図によると山道もあるようだ。どうやら民家の手前を右に折れる道がそのようだが、雨のこともあり、安全策をとり、そのままの車道を東笠取方面に向かった。しかし、車道といってもこの峠を歩いている間、結局一台も車は来なかった。 後ろから男性が来られた。僕たちと同じようなザックを背負われている。足が速い。道にも慣れておられるようだ。簡単な挨拶をされ、去っていかれた。 10:30夕映えの一本杉<写真13>到着。ここも笠取八景のひとつのようだ。三叉路になっているので、ここで山道と合流なのだろう。 三叉路を左へ向かう。すぐ下に神社があった。10:40東笠取の集落<写真14>に到着。前から車が一台来た。地図を眺めておられたので地元の方ではなさそうだ。 柿がたくさんなっていた。たぶん渋柿なのだろうと思ったが、ほとんど車も来ないところだから、甘くても誰も取らないのかも知れない。 しばらくやんでいた雨がまた降り出してきた。木の陰に入り、レインウェアを取り出し、着用した。雨の中、道なりに進んで行くと、別れ道<写真15>に出た10:55。 右へ道なりにそのまま進むと岩間寺まで30分。左へ山へ向かうと奥宮神社を経て岩間寺へ40分。天気予報では午後が晴れてくるということだったので、琵琶湖展望台もある奥宮神社への道を歩くことにした。 今日、三度目の登りだ。ペースを一定に保ち、山道を登った。 |
|||
 <写真12 アクトパル宇治> |
||||
 <写真13 夕映えの一本杉> |
||||
 <写真14 東笠取の集落> |
 <写真15 奥宮神社への分岐> |
|||
| ・・・ 西国十二番岩間寺にて ・・・ 11:23琵琶湖展望台<写真16>到着。雨は上がらなかったので、期待していた展望は当然ない。展望台から道路をはさんだ向かい側に雨宿りのできる建物があった。ちょうどいい時間なので、昼食とした。僕はおにぎり2個。伊三郎氏はカロリーメイトだ。 山を歩くのだから、もっといいものを食べたらと言われることがあるが、毎日歩くわけでもないので、山歩きをする時は、簡単なものでいいと思っている。 雨は相変わらず降っているので、奥宮神社は、よそうと思ったが、本殿がすぐ上にあるようなので昼食後、行ってみた。この神社は最近できた新しいもののようだった。 奥宮神社をあとにし、岩間寺へ向かった。ここからはほぼ水平道だ。途中、車、自転車止めの柵を越えて、11:55西国十二番岩間寺本堂<写真17>に到着した。 ここまでほとんど人と出会わなかったのに、岩間寺には、たくさんの人がおられ、驚いた。濡れたレインウェアでは、迷惑がかかりそうなので、お参りはしばらく待つことにした。 本堂脇の椅子にご高齢のお坊さんが座っておられた。この方はレインウェア姿の僕たちを見て、「上醍醐から歩いて来られたのか」と、訊ねられた。 「そうです」と答えると、「雨の中、ご苦労様です」とおっしゃられ、雨の中、資料を取りに行かれ、岩間寺境内の蓮や松尾芭蕉の詠んだ池<写真18>など案内説明をして下さった。 この方、50年ほど前に、托鉢をしながら75日をかけてお四国も歩かれたそうである。今は、寺務を終えられ、岩間寺にお参りされる人を合掌して迎えることを行としているとおっしゃていた。 人が少なくなってからお参りをし、本堂をあとにし、12:15仁王像前<写真19>を通過し、岩間寺をあとにした。 大きな駐車場には、多くの車や、観光バスが停まり、昼食のできる会館は大勢の人で賑わっていた。 ここからアスファルトの車道を下った。京滋バイパスを越え、新しく造成されつつある墓園を眺めながらさらに下った。バス通りに出た。滋賀大西門<写真20>。多くの車が往来し、民家もたくさんあった。 |
 <写真16 琵琶湖展望台> |
|||
 <写真17 岩間寺本堂> |
||||
 <写真18 松尾芭蕉の古池> |
||||
 <写真20 滋賀大西門> |
 <写真19 仁王像前> |
|||
 <写真21 石山寺東大門> |
・・・ 西国十三番石山寺にて ・・・ 地形図によると、もう一度京滋バイパスを交差したら、しばらくで石山寺のようだ。京滋バイパスを越えた。しかし、そのまま京滋バイパスと直交する北西方向の道路を歩いてしまった。 1kmほど行き過ぎたところで、引き返す恰好になったので30分ほど余計に歩くことになったが、石山寺への巡礼道に戻り、13:50西国十三番石山寺東大門<写真21>に到着した。 ここには、岩間寺よりさらに広い駐車場があり、多くのバスやタクシーが停まり、土産物屋<写真22>が軒を連ねていた。 東大門をくぐり参道を歩いた。その先は拝観料500円が必要だった。大きなお寺なので維持も大変なのだろう。 中に入り、石段を登る。雨はよく降っている。本堂階段下の蓮如堂に雨が避けられる軒があった。ここでペット茶を飲みながら、少し休んだ。 メイン参道のはずだが、雨なので人通りは少ない。 小休憩のあと、本堂<写真23>へ向かった。大きい。太い柱が何本もある。お参りをしたあと、本堂から景色を眺めた。ここもまだ紅葉には早いようだが、ところどころ色づいている。霧がかかっていいムードだ。 本堂をあとにし、上へと向かった。日本最古の多宝塔<写真24>があった。さらに境内の奥へ。小町像があった。 最後は、無憂園<写真25>に。結局、境内を一周し、14:45石山寺東大門をあとにした。 京阪石山寺駅に向かった。距離800mをちょうど10分で到着。14:59発坂本行きに乗車。まっすぐ帰るには少々早いので、皇子山まで乗り、スーパー銭湯「やまとの湯」で汗を流した。 そのあと、僕はJR西大津駅から京都駅を経てJRで宇治に戻った。 伊三郎氏は、朝、上醍醐寺参道で借用した金剛杖を返すため、JR山科駅で下車され、京阪バスで醍醐寺に向かわれた。 |
|||
 <写真22 軒を連ねた土産物屋> |
||||
 <写真23 石山寺本堂> |
||||
 <写真24 多宝塔> |
 <写真25 無憂園> |
|||
2003年11月5日 記
 |
 |
|
| お遍路記録へ戻る | TOPへ戻る |