肉による食中毒を防ぐには家の台所でも注意が必要です。
食中毒を引き起こす腸管出血性大腸菌、カンピロバクター、
サルモネラ菌などの細菌は熱に弱く、
十分加熱すれば肉は安全に食べられる。
ただ、調理の手順によっては他の食品に菌を移す可能性がある。
と言われている。

食中毒を防ぐ肉料理の段取り
肉による食中毒を防ぐには家の台所でも注意が必要です。 食中毒を引き起こす腸管出血性大腸菌、カンピロバクター、 サルモネラ菌などの細菌は熱に弱く、 十分加熱すれば肉は安全に食べられる。 ただ、調理の手順によっては他の食品に菌を移す可能性がある。 と言われている。 |
 |
まな板と包丁の使い方が重要なポイント。
肉を切った後のまな板、包丁で板わさ用にかまぼこを切ったとすると、
細菌がかまぼこに移り、そのまま口に入ることになる。
できれば、まな板を2枚用意する。
1枚は野菜サラダ、ハム、ちくわ、チーズ、パンなど
そのまま熱を加えずに食べる食材用。1枚だけなら裏表で使い分ける。
 |
うすい下敷きのようなまな板を生の肉、魚専用に準備し、 本来のまな板の上に置いて切ると細菌が移りにくい。 切り開いて平らにした牛乳パックを使ってもよい。 包丁もまな板も使うたびに洗剤で洗うのが基本。 生肉を触った菜箸やトングが サラダ用の生野菜に触れないことも必要。 |
盛り付けにも工夫が必要。 完成した肉料理を生野菜と一緒に長時間置くのは避ける。 肉は加熱で細菌が死んでいるが、 生野菜についた菌が肉へ移ることがあるからである。 細菌はアミノ酸を利用して増殖する。 野菜では増殖が抑えられていた細菌が、 肉に移るとアミノ酸が豊富になるので急速に増える。 お弁当に生野菜を入れる場合も、 肉のおかずとは別容器に入れるほうがよい。 またはラップやホイルで仕切って直接触れないようにする。 サンドイッチはパン・トマト等の生野菜、 具をあらかじめはさむのではなく、 別にして食べる際にはさむほうが安全です。 |
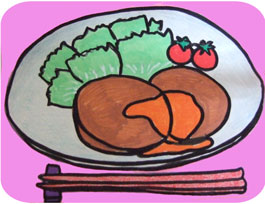 |
| 後片付けでは乾燥が大切。 スポンジは水分と汚れが残り雑菌が繁殖しやすい。 洗い物の最後に湯沸かし器からのお湯で 丁寧にもみ洗いし、絞って乾燥させる。 数日に1回は熱湯で5分煮る煮沸消毒を習慣にする。 台ふきんも濡れたまま放置しがち。 臭うようなら雑菌が繁殖している証拠。 熱湯で煮て殺菌をする。汚れをふき取るたびにこまめに洗う。 ふきんかけにかけておくと乾きやすい。 水切りかごもたまった水を捨て、洗う。 汚れがたまりやすい四隅は丁寧に洗う。 漂白剤が使える素材なら2〜3日に1回殺菌しましょう。 |
 |