この季節、突然の高熱が出たら、
まずインフルエンザが疑われます。
できれば、
解熱剤や風邪薬
(熱を下げる成分が含まれていることがあります)
を使わずに熱の様子をよくみましょう。
薬を使って熱を下げてしまうと、
熱が続いているのかどうか
分かりにくくなることがあります。
水分を十分補給して
脱水症状に気をつけながら
医療機関を受診しましょう。

《インフルエンザのおはなし》
| 〜インフルエンザかな?と思ったら〜 この季節、突然の高熱が出たら、 まずインフルエンザが疑われます。 できれば、 解熱剤や風邪薬 (熱を下げる成分が含まれていることがあります) を使わずに熱の様子をよくみましょう。 薬を使って熱を下げてしまうと、 熱が続いているのかどうか 分かりにくくなることがあります。 水分を十分補給して 脱水症状に気をつけながら 医療機関を受診しましょう。 |
 |
 |
医療機関では受診時、 医師の判断でインフルエンザかどうかの 簡易検査を行います。 鼻の奥や喉の粘膜を綿棒でこすって インフルエンザウイルスがいるかどうかを チェックする検査です。 高熱が出てからあまり時間がたっていないと、 反応が出ないことがあります。 そうした場合、反応が出なかったからと言って インフルエンザではないとは言い切れません。 もうしばらく熱の様子をみていく必要があります。 |
〜インフルエンザに罹っていたら〜
インフルエンザウイルス陽性の結果が出た場合、
発症して(熱が出始めて)48時間以内ですと、
抗インフルエンザ薬(タミフル・リレンザ)の服用が効果があります。
これはインフルエンザウイルスの増殖を抑えるものなので、
48時間以上たってウイルスが増え切ってしまっては、効果は期待できません。
抗インフルエンザ薬を適切な時期に服用した場合、
2日くらいで熱は下がります。
しかし、インフルエンザウイルスはまだ身体の中に残っています。
熱が下がっても処方された日数分、最後まで飲みきってください。
またウイルスがまだ身体に残っているということは、
周りの人にインフルエンザをうつす可能性があるということです。
学校保健法ではインフルエンザは感染の拡大を防ぐため、
公欠扱いとなり、熱が下がってから丸2日経つまで
出校停止ということになっています。
お仕事をされている方は事業所によって扱いがいろいろですので、
職場にインフルエンザであることを伝え、出勤時期の相談をして下さい。
抗インフルエンザ薬を飲まなかった場合、高熱が5日ほど続きます。
熱が下がっても解熱後2日くらいは自宅で安静にして過ごしましょう。
薬を服用しても、服用しなくても、
症状が治まるまで水分補給をしっかり行い、安静にして過ごします。
部屋の湿度はやや高め(70%前後)に保つと理想的です。
発熱すると熱を下げようと身体から水分が放出されます。
脱水症状を防ぐためにも水分は努めて摂るようにしましょう。
脱水症状を起こすと、全身の細胞の働きが低下します。
喉の渇きや、尿量の減少などが脱水症状のサインです。
効率よく水分補給をするには、スポーツドリンクなどを利用するとよいでしょう。
また体力を落とさないように栄養補給も大切です。
食欲がない時は少しでも消化がよく、温かい食べ物を摂りましょう。
温かい食べ物を摂ると鼻・のどなどの粘液の分泌が多くなり、
ウイルスを排除する機構が活発になります。
熱のある時はヨーグルトやプリン、ゼリーなど
冷たくてのどごしの良いものもよいでしょう。
インフルエンザにかかると高熱で体力が落ちるため、
細菌による肺炎などの合併症を起こすことがあります。
特に小さいお子さんや高齢者など、抵抗力が弱い方は要注意です。
熱が長引く、いったん下がっていた熱がまた出てきた、
痰や鼻汁が黄色や緑色になってきたというようなことが起こってきたら、
二次感染をおこしている可能性が高いので早めに受診しましょう。
インフルエンザは非常に感染力が強いため、
家族や周りの人にも感染する可能性が高くなります。
小さい子供さんや高齢者がおられる方は特に注意し、
本人も家族もマスクの着用、手洗い、うがいを頻回に行い、
感染予防に努めてください。インフルエンザの潜伏期間は3日ほどと言われています。
もし感染した場合、3日ほどで症状が出てくるので気をつけましょう。
インフルエンザはA型のウイルスとB型のウイルスがあります。
ウイルスの型が違うのでどちらか一方のインフルエンザにかかった場合、
もう一方のインフルエンザにも感染する可能性があります。
インフルエンザに一度かかったから大丈夫と安心せず、
引き続き感染予防に努めることが大切です。
| 〜予防注射を受けた人でも〜 また予防注射を受けた方でも、抗体のでき方、 減り方は人によって違いますので、 絶対インフルエンザに感染しないということはありません。 周りにインフルエンザの人がいたら、積極的に感染予防に努め、 症状が出たら予防注射を受けたから普通の風邪だと侮らず、 速やかに医療機関を受診することをお勧めします。 |
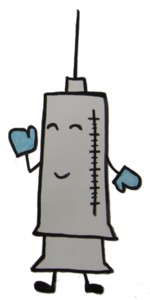 |